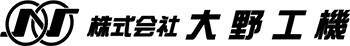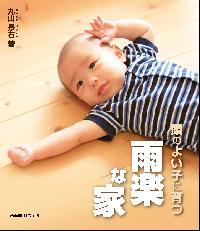周辺にがけ(崖)のある土地に家を建てたい場合、がけ条例によって建築が制限される恐れがあります。
しかし、「がけ条例とは何か」「がけがある土地には家を建てられないのか」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、岐阜県の土岐市や恵那市などで家づくりを手がける工務店“大野工機”が、家を建てる際に注意したいがけ条例とは何か詳しくお伝えします。
●がけが切土で堅固な場合や、擁壁を設置する場合などは、制限が緩和されます。
●各自治体で制限が異なるので、信頼できる施工業者に相談し、理想の住まいを建てられるのか確認してみましょう。
目次
コンテンツ
がけ条例(崖条例)とは

がけ条例(崖条例)では、がけに近接する敷地で建築する際に、がけの上下ともに建築が制限されます。
「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」(建築基準法第19条4項)という法令に基づいて、各自治体が定めている条例です。
条例の内容は自治体によって異なり、岐阜県においては次の通りに制限されています。
(がけに近接する建築物の制限)
第六条 高さ二メートルを超えるがけ(人為的に造成された急傾斜地をいい、小段等により上下に分離するがけは一体のがけとする。以下同じ。)の上若しくは下又はがけ面においては、当該がけの上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物を建築してはならない。
例えば、がけの高さが3mの場合、中心線から水平3m以内の場所に住居を建てることは不可能です。
また、岐阜県に隣接する愛知県においては、次の通りに定められています。
(がけ附近の建築物)
第8条 建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
この場合、仮にがけの高さが3mなら、がけの下端あるいは上端から6m以上離れていなければ家を建てられません。
上記の通り、がけ条例と一口に言っても各自治体で細かな内容は異なるため、家を建てる前に確認しておきましょう。
ちなみに、がけとして扱われる土地は、高さ2mを超えており、なおかつ30度を超える傾斜のある土地とされています。
がけ条例の緩和条件

がけ条例によって建築が制限されている土地でも、次の条件に当てはまる場合は家を建てられる場合があります。
- ・がけが切土であって堅固な地盤である
- ・擁壁を設置する
- ・がけの下に建築する場合、構造条件を満たしている
- ・防災上必要な措置が講じられている
それぞれの内容について詳しく確認していきましょう。
がけが切土で堅固な地盤である
切土とは、丘陵地などの傾斜のある地面を削り、平らにした部分です。
がけが切土であり、なおかつ圧縮強度の高い堅固な地盤だった場合は、地盤の崩壊リスクが比較的抑えられます。
そのため、土砂災害による影響も少ないと想定され、がけ条例による建築制限が緩和される可能性があります。
安全性について確認するためには、地質調査などを通じて地盤の強さを証明する必要があるため注意しましょう。
擁壁を設置する
擁壁とは、がけのような高低差のある土地において、土砂の流出を防ぐために設置される壁です。
コンクリートやブロックで作られており、がけ崩れ・土砂災害のリスクを抑えることができます。
しかし、がけと家の間に壁を設置したからといって、すべてが擁壁として扱われるわけではありません。
擁壁として認められ、がけ条例の規制が緩和されるには、次の条件を満たす必要があります。
- ・法第 88 条第1項に規定する工作物の確認を受けたもの
- ・都市計画法第 29 条第1項又は第2項に基づく開発許可を受けたもの
- ・宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第1項の規定による許可を受けたもの
上記を満たしていない場合、擁壁には該当しないため注意しましょう。
がけの下に建築する場合の構造条件を満たす
がけの下に家を建てる場合、基礎ぐいを除く構造耐力上主要な部分に、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を採用すると、がけ条例による制限が緩和されます。
堅牢な構造になることで、がけ崩れや土砂災害時にも住宅の安全を守りやすいと判断されるためです。
また、土砂が流入してくるリスクを抑えるために、がけに面した方向には外壁の開口部を設けられません。
制限緩和を受けるには、堅牢な構造の採用と、開口部の位置のどちらの条件も満たす必要があるため注意しましょう。
防災上必要な措置を講じる
上記以外にも、がけ崩れ・土砂災害によるリスクを下げるために効果的な対策を講じることで、がけ条約の制限が緩和される場合があります。
岐阜県建築基準条例にて、防災上必要な措置として挙げられているのは次の2点です。
道路の築造により生じた崖及び堤防等については、その施工者及び管理者が地方公共団体等である場合
都市計画法第 29 条に基づく開発許可や宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条に基づく許可において、各許可を行ううえでの技術基準に基づき1:1.5以下の勾配とした切土法面については、各法令手続きに基づき検査済証の交付を受けている場合
その他、どのような措置を講じることで制限が緩和されるのかは、施工業者へ相談しましょう。
がけ条例では排水設備にも注意
がけ条例では、建築位置に関する制限だけでなく、排水設備に関する制限にも注意が必要です。
岐阜県建築基準条例では、「高さ二メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない」と定められています。
雨水や汚水が下に流れ、擁壁の裏側やがけに浸透することで、土砂崩れを引き起こさぬように設けられた制限です。
がけ条例が適用される場合の注意点

がけ条例が適用される土地に家を建てる場合、次の3点に注意しましょう。
追加コストが高くなる恐れがある
がけ条例が適用される土地に家を建てる際、擁壁の設置工事を行うとなると、追加コストが高くなる恐れがあります。
擁壁工事の費用目安は1㎡につき3〜10万円前後と考えられるため、擁壁の設置だけで数百万円ほどかかるケースもめずらしくありません。
また、すでに擁壁が設置されている土地に家を建てる場合も、老朽化が進んでいる場合は解体が必要です。
そのため、追加のコストがさらに膨らむ恐れもあります。
「土地代が安いと思って購入してみたら、擁壁工事などで予想以上にコストがかかった」と失敗するのを防ぐために、事前の調査や見積もり、資金計画は慎重に行いましょう。
災害リスクについて十分に考慮する
がけ条例が適用する土地は、他の土地と比較すると災害リスクが高いと考えられます。
擁壁を設置するほか、規定の構造条件を満たすことで家を建てることはできますが、災害リスクがゼロになるわけではありません。
自治体のハザードマップでどのようなリスクがあるのか確認し、地盤改良など十分に対策を講じた上で家を建てましょう。
信頼できるプロに相談する
がけ条例が適用となる土地で家を建てる場合、信頼できる専門家への相談が欠かせません。
がけに近接した土地で家を建てるとなると、次のようなトラブルが発生するケースもあるためです。
- ・せっかく土地を購入したのに、がけ条例の影響で希望通りの間取りにならなかった
- ・建築コストが予想以上にかかった
- ・既存の擁壁が老朽化しており、条件を満たせず家が建てられない
上記のような事態を防ぐためには、がけ条例に対応した家づくりに強く、施工実績の豊富な業者に相談する必要があります。
信頼できる施工業者に依頼し、土地探しから家づくりまで総合的にサポートしてもらいましょう。
まとめ

がけに近接する土地に家を建てたい場合、「がけ条例」として建築できる位置や排水設備に制限があるため、各自治体における条例を欠かさず確認する必要があります。
「条例を確認してみても難しい」「この土地に家を建てられるのか知りたい」とお困りの方は、まずは信頼できる施工業者に相談し、理想の住まいを建てられるのか確認してみましょう。
大野工機では、1969年の創業以来、デザイン・機能ともに優れた家づくりを提供しており、がけに近接する土地での家づくりも多数手がけてきました。
土地探しや補助金についても詳しくご説明させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大野工機は、昭和44(1969)年創業以来、総合建築会社として岐阜県東濃地域を中心に『顧客第一』をモットーとして“一生の宝物”となる住宅を作り続けています。
● 美しいデザインをつくります
● “ぎふの木”の家づくりにこだわります
岐阜県東濃地域で家づくりを始めたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。